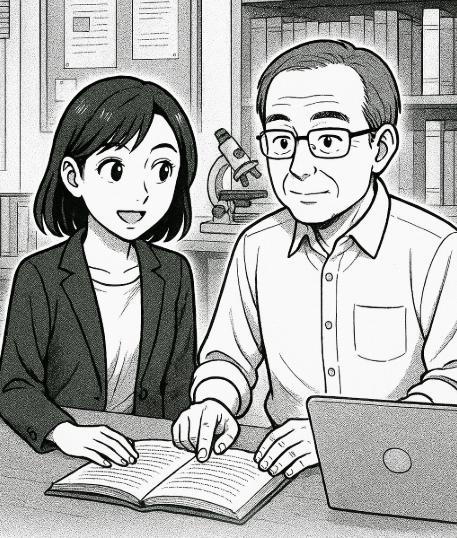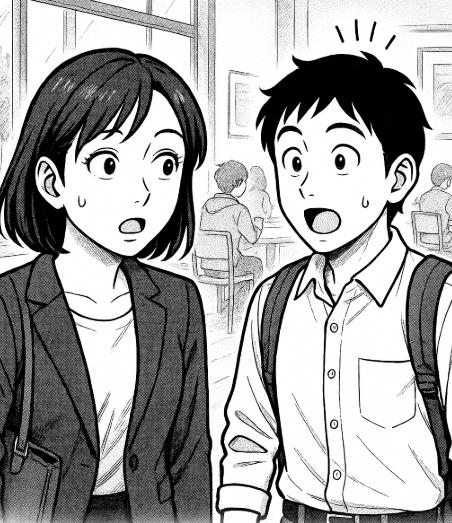
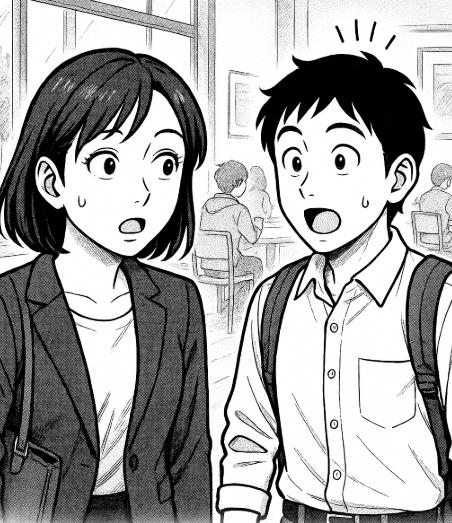
私が“童貞”に惹かれる理由
人から見れば、私は少し変わっているのかもしれない。
付き合う相手に求める条件はただ一つ──童貞であること。
別に、支配欲があるわけでも、優越感を得たいわけでもない。
むしろその逆。
“誰かに触れられたことがない純粋な心”に、私は心から魅力を感じる。
初めての緊張、不器用な仕草、ぎこちない目線。
それらすべてが、嘘のない「本当の人間らしさ」だと思えるから。
経験豊富な男の人は、私を安心させてくれない。
心の奥まで覗かれるようで、どこか居心地が悪い。
でも童貞の子は──とても素直で、優しい目をしている。
そんな“まだ知らない世界”にいる子に出会えるのは、もう大学でしかない。
そう思っていた矢先、あの子を見つけた。
カフェで出会った、気になる後輩
キャンパスのカフェテリアは、騒がしいけれど、私のお気に入りの場所だ。
その日、私は卒論資料を片手に、静かな午後を過ごそうとしていた。
ふと、視線の先に座席を探す男の子がいた。
痩せ型で、清潔感はあるけれど、どこか所在なげに歩いていて──
目が合った瞬間にわかった。
「……あの子、たぶん童貞だ」
感覚でわかる。たぶん私だけが持ってるセンサー。
童貞センサー。
自分でも笑ってしまいそうになるけれど、これは長年の“研究成果”みたいなもの。
彼の動きはぎこちなく、目は純粋で、誰とも交わろうとしない壁のようなオーラを纏っていた。
でも、不思議と気になった。今までのどの子よりも。
「ここ、空いてるよ」
私は自然なトーンで声をかけた。
彼は驚いたように一瞬戸惑いながら、そっと座った。
そこから、物語が始まった。
「君、童貞でしょ?」と声をかけた日のこと
何か話そう。だけど、どう切り出すべきか。
でも私には、いつも使う“必殺ワード”があった。
「ねえ、君さ……童貞でしょ?」
彼は驚きすぎて味噌汁を吹き出しそうになった。
うん、やっぱりそうだ。間違いない。
「図星?」
焦って言い訳をする彼の顔が、あまりにも可愛くて、思わず笑ってしまった。
ああ、この反応。この初々しさ。
やっぱり、私はこの感じが好きなんだなと改めて思った。
「ご、ごめんなさい……」
そう言った彼に、私はとっさに返した。
「なんで謝るの?私、童貞くんって、好きだよ」
嘘でも冗談でもない。これは、私の本音だった。
彼との距離が縮まる時間──好きになっていく
それから私たちは、自然とカフェで会うようになった。
彼の名前は、田島優斗(たじま・ゆうと)くん。
2年生で、工学部。話し方は穏やかで、常に周囲に気を配るような子だった。
最初はただの興味だったのに、いつの間にか、
「今日も会いたいな」「次、いつ会えるかな」と思うようになっていた。
彼と話す時間は、安心する。
誰かに素直に“いい子だね”って言いたくなるなんて、人生で何度あるだろう?
ある日、私は彼に言った。
「そろそろ、うち来てみる?」
彼は一瞬戸惑っていたけど、目は逃げなかった。
「別に、そういう意味じゃないよ?……でも、したくなったら、してもいいよ」
そのときの彼の顔が、頭から離れなかった。
初めての夜、彼に伝えたかったこと
その夜、彼は私の部屋に来た。
ぎこちなく、でも真っ直ぐに、目をそらさずに私を見ていた。
「緊張してる?」
と聞いたら、彼は正直に「うん」と答えた。
私は、心の中で「この人の“初めて”を、ちゃんと受け止めたい」と思った。
彼の手が震えていたから、私は自分からそっと触れた。
「大丈夫、焦らなくていいよ」って、何度も伝えた。
私にとって“初めてをもらう”ということは、体のことじゃない。
その人が自分をどう信じて、心を預けてくれるか、そこが一番大事なんだ。
彼は最後まで、とても優しくて、純粋だった。
その温もりを肌で感じながら、私はふと泣きたくなった。
それは、悲しさでも、後悔でもなく──きっと、幸福だったから。
朝、私は彼に伝えた。
「ありがとうね。君の初めて、もらえて嬉しかった」
彼が恥ずかしそうに笑って「……俺もです」って言ってくれたとき、
この出会いは間違いじゃなかったと思った。