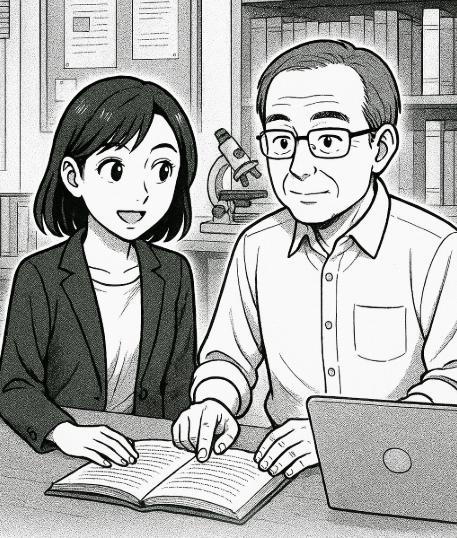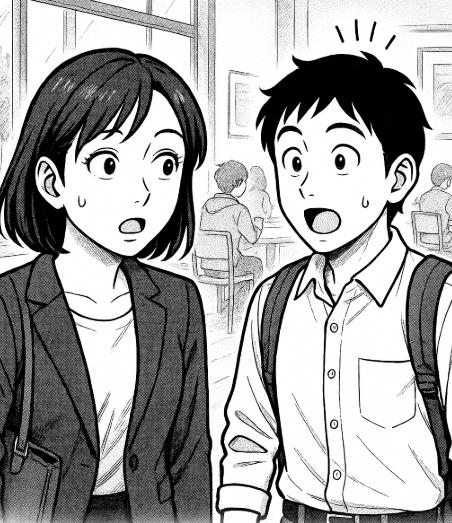カフェで初めて出会ったあの日から、もう数週間が経っていた。
優斗くんが私の部屋で童貞を卒業した、あの夜のことは今でもはっきり覚えている。
緊張して、目も合わせられず、触れる手は震えていた。
でもその震えの中には確かに「まっすぐな気持ち」が宿っていて、それが私をどこまでも満たしてくれた。
あの夜以降、私たちは“付き合っている”という形にはしていなかったけれど、週に2〜3回は会って、自然と肌を重ねるようになっていた。
私が“教える側”になった理由
「ねえ、触るのってこれで合ってる?」
「ゆっくり?それとも……強め?」
「キスって、こんな感じでいい?」
彼は何度も何度も私に聞いてきた。
そのたびに私は「うん、上手になってきたよ」と微笑んで、体を委ねた。
教えることが、こんなにも心をくすぐるものだなんて、思ってもみなかった。
まだ少し恥じらいを残す彼の指先。
舌が触れるときのぎこちない息。
腰を動かすときの、迷いと興奮が入り混じった目。
全部が、愛おしかった。
ただひとつ──
そろそろ彼に、“自信”を持たせてあげたかった。
「今日は、イカせてみて?」
ある夜、彼がシャワーを浴びて戻ってきたタイミングで、私はベッドに寝転びながら静かに言った。
「ねえ、今度は私をイカせてみて?」
彼は、バスタオルを腰に巻いたまま固まった。
「……え?」
「いつも私がリードしてるでしょ?今度は、優斗くんが主導でやってみてよ」
挑戦的な笑みを浮かべながら私がそう言うと、彼の喉がごくりと鳴った。
「……できるかな」
「できるよ。だって、もう童貞じゃないでしょ?」
そう囁くと、彼の目が少しだけ変わった。
男の子から、男の目に。
優しさと強さが入り混じる指
シーツの上に仰向けになった私に、彼はそっと覆いかぶさる。
「じゃあ……キスから、するね」
柔らかく唇が重なった。最初のころと違って、舌の動きも、リズムも上手になっている。
何度も練習してきた証拠。
「ん……優しくて、上手になったね」
そう囁くと、彼は少し照れながらも、唇を首筋に落とした。
そのまま鎖骨、胸元、そしてゆっくりとお腹の方へ。
彼の手が、私の下着に触れた瞬間、私は少しだけ体を震わせた。
「ここ……触っていい?」
「もちろん。いっぱい触って、確かめて」
彼の指先がショーツ越しにそっとなぞる。
まだ優しすぎるくらいの触れ方だったが、それがかえって私の奥をくすぐった。
彼は何度も私の表情を確かめながら、慎重に指を中へ──
「あっ、ん……そこ、気持ちいい……」
戸惑いながらも、少しずつ動かし方を探るように、彼の指が動く。
最初は控えめだった動きが、私の反応を見て、徐々に確信に変わっていくのがわかった。
「あ……そこ、もっと……いい、上手だよ……」
「ここ?この角度で……?」
「そう、そこ……っ、ああ……」
息が熱を帯び、腰が自然と浮いていく。
彼の指はもう、立派な“男”のものになっていた。
自信を得た彼の瞳に、私は堕ちる
しばらくして、私の膝を両手でそっと開き、目線を合わせてこう言った。
「……してもいい?」
「もちろん」
そう答えると、彼は迷わず私の中へ入ってきた。
最初よりもスムーズで、深く、丁寧に。
「……優斗くん、すごく上手になったね……」
「もっと気持ちよくなってもらいたくて……。俺、今日……絶対イカせたい」
その言葉だけで、もう何度でもイケそうだった。
腰の動きがしなやかになり、角度を微調整してくる彼。
私の敏感なところをしっかり覚えていて、何度もそこを突いてくる。
「あっ、ダメ、それ……ああ……ッ、すごい、イッ……」
自分でも驚くほど激しく、私は達してしまった。
彼の胸に爪を立てながら、ビクビクと震える自分の体。
彼はその様子を、じっと優しい目で見つめていた。
「……ちゃんとイカせられた?」
事後、私が息を整えていると、彼が少し不安そうに尋ねた。
「……ちゃんとイカせられた?」
私は笑って、彼の髪を撫でる。
「うん、バッチリ。完璧だった」
「……よかった」
その瞬間の彼の表情は、今まで見たどんな笑顔よりも自信に満ちていた。