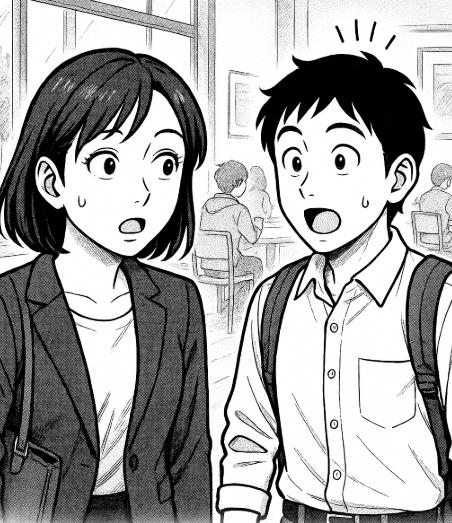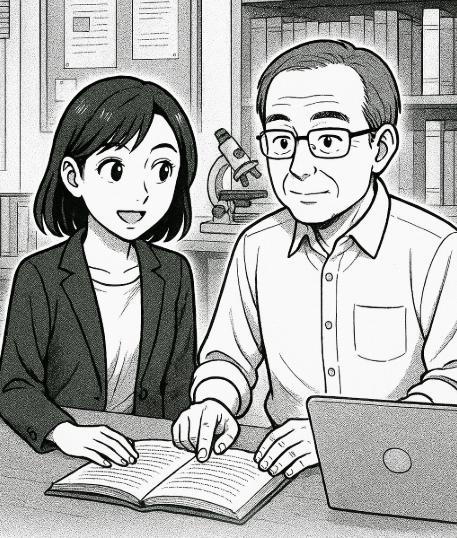
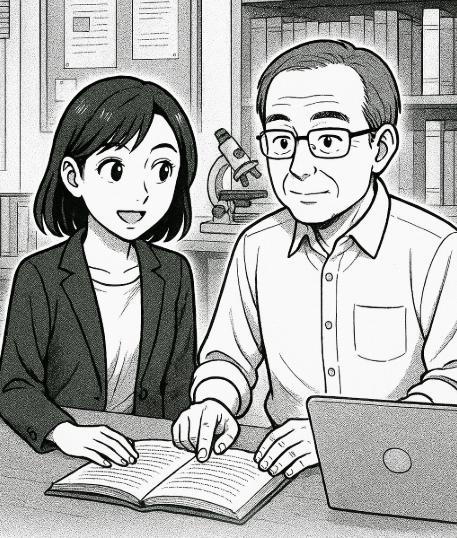
優斗くんには、言っていないことがある。
カフェで偶然出会い、彼の童貞をもらってから、私たちは自然と関係を深めていった。
彼の純粋さに心がほどけていくようで、それはとても幸せな時間だった。
でも──
それとは別に、私は毎週金曜日の夜、決まった部屋で別の男に抱かれている。
50歳の、既婚の男。
名前は加納 雅彦(かのう まさひこ)。
加納さんは、男の「完成形」だった。
彼との出会いは偶然じゃない。
大学3年のとき、インターン先で知り合った。
物腰は静かで、話すテンポは遅い。
でも言葉の一つひとつに“重さ”があって、妙に惹きつけられた。
最初に誘われたのは、仕事が終わった帰り道。
「君、話し方が落ち着いてるね。よかったら、食事でもどう?」
そのときから、何かに飲み込まれる予感はしていた。
彼は独特の空気をまとっている。
無理に支配することはしないのに、こちらが自然と従ってしまう。
“歳を重ねた男”にしか出せない、余裕と温度差のある視線。
ベッドの中でも、それは変わらなかった。
「遥、おいで」その一言で、私はすべてを許す。
週に一度だけ、彼の借りているマンションの一室で会う。
そこには時計がない。
時間の感覚も、罪悪感も、すべてが麻痺していく。
「遥、おいで」
ソファに座ったまま、片手でスコッチグラスを傾けながら、私を手招きするその姿。
ネクタイを緩めたシャツの隙間から覗く鎖骨、熟れた男の香水とタバコの匂い。
それだけで、身体が自然に熱くなる。
「今日も、いい子にしてた?」
「うん……たぶん」
「嘘つけ。お前、また誰かの男、手出しただろ?」
彼は冗談めかして言うが、その声は低く、喉の奥で鳴っている。
手が、太ももを這い上がり、下着の上から撫でられる。
「……でも、そういうとこが好きなんだよ。お前の“汚れ方”がちょうどいい」
年下の彼との“愛”では、満たせないもの
優斗くんは、まっすぐで、優しくて、本当にいい子。
彼といると、心が温まる。
でも──濡れるのは加納さんの指だけ。
荒く、意地悪に、私の浅ましさを引きずり出すような動き。
強引で、でもどこか悲しい背中。
そういう男に壊される感覚が、たまらなく、快感だった。
ベッドの上で、加納さんは言う。
「お前さ……あのガキのどこがいいの?」
「ガキじゃないよ。大事な子」
「じゃあなんで俺の前で、こんな声出してんの?」
言い返せない。
喘ぎ声が止まらないから。
「遥ってさ、他の男に“好き”とか言いながら、結局は俺で締まるんだよな」
一発、一発、彼の言葉が突き刺さる。
腰を掴まれ、脚を開かされ、好きなように扱われる。
でも……嫌じゃない。
むしろ、そこに“自分の本性”を見つけてしまう。
愛されたい私と、壊されたい私
彼に抱かれながら、私はよく考える。
優斗くんのような真っ直ぐな子と、
加納さんのような“壊す側の男”と、
どちらといるときの自分が「本当の私」なんだろう?
優しくされて満たされるのも好き。
でも、蹂躙されて快楽に堕ちていくのも、嫌いじゃない。
ベッドの中で、加納さんが吐き捨てるように言った。
「どうせお前、どっちも選べねぇんだろ?」
私はただ、黙って笑った。
だって──図星だったから。
「遥、お前は誰の女だ?」
金曜日の夜。
ホテルのベッドで、加納さんが私の耳元で囁いた。
「遥、お前は誰の女だ?」
彼の腰の動きが激しくなるたびに、問いは強くなっていく。
私は何も答えず、ただ抱きつく。
中に残る彼の熱を、全部感じながら。
たぶん、私は誰のものにもなれていない。
だからこそ、誰のものにでもなれる女でいたいのかもしれない。
ラスト:あの子には、言えないこと
翌朝、加納さんより少し早くベッドを抜け出す。
キッチンでコーヒーを淹れ、カップを揃えて置いた。
ふと、スマホにメッセージが届く。
優斗くん:
「今日、会えますか?」
私は少しだけ微笑んで、メッセージを返す。
「うん。もちろん」
コーヒーの香りに包まれながら、思う。
“あの子には、絶対に言わない。”
この関係は、あの子がまだ知らない私の一部。
それでいい。
きっと、それが“大人の恋”ってやつなんだと思う。