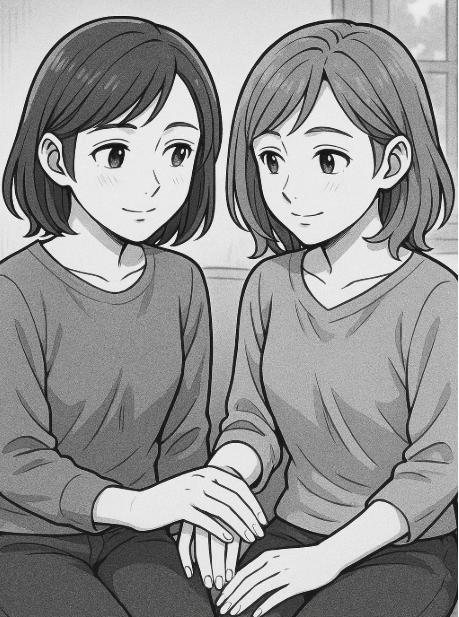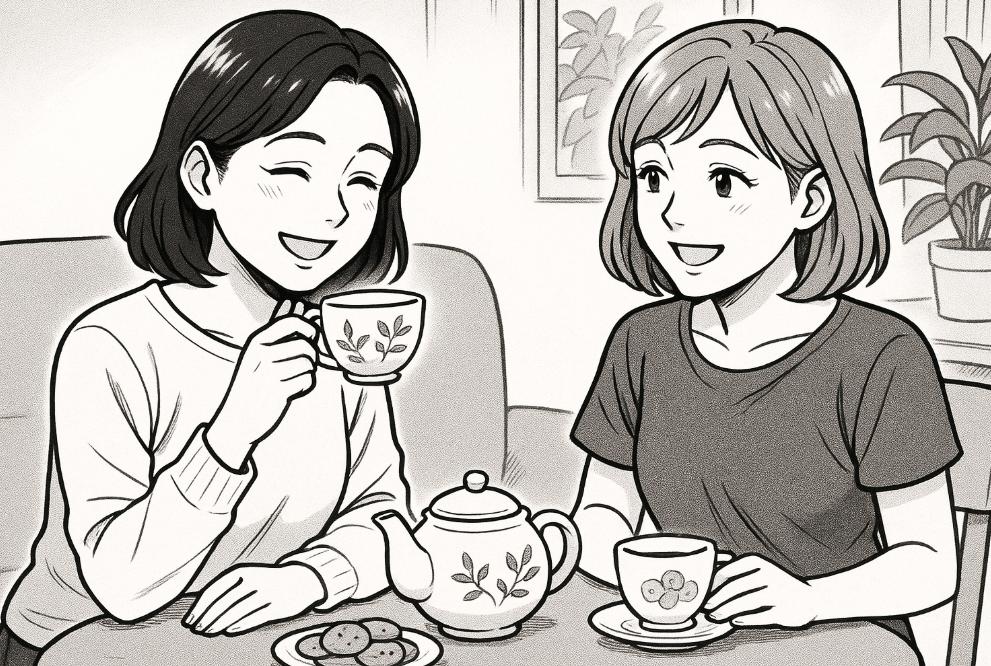「ねえ、ワイン飲む?ちょっとだけ」
午後のお茶が終わったあと、気づけばグラスに赤が注がれていた。
「お昼からワインなんて……」
「たまには、いいでしょ。旦那、今日は遅いって言ってたし」
笑いながら言うと、彩香さんも小さく微笑んだ。
すぐに頬が赤くなる。お酒が弱いのかもしれない。
彼女は、なんというか──ずっと緊張してるみたいな人だった。
いつも微笑んでるけど、その奥にずっと「我慢」がある気がしてた。
たぶん、私と同じように。
二人きりの空間、柔らかな沈黙
カーテンの隙間から差す午後の光が、ふたりをぼんやり包んでいた。
テレビもつけず、スマホもテーブルに伏せて。
「……あのね、彩香さん」
「ん?」
「さっき、“寂しい”って言ってたよね」
「うん……言ったかも」
「それって、体のことも?」
彩香さんの手がピクリと動く。
言葉は返ってこない。
でもその沈黙が、肯定よりもずっと色っぽかった。
ゆっくりと、距離を詰めていく
私は自然な流れを装って、彩香さんの隣に移動した。
彼女は少し戸惑った顔をしたけど、拒まなかった。
「指、冷たいね」
そう言って、彼女の手に自分の指先を重ねる。
手の甲をなぞるように滑らせると、彼女のまつげがわずかに震えた。
「……梓さん、なにして……」
「何もしないよ。触れてるだけ」
目は合わせずに、声だけを落ち着かせる。
指先が手首から、腕へ、
そして二の腕をゆっくりと撫で上げる。
触れる場所はまだ“普通”なのに、
彩香さんの呼吸が少しずつ変わっていくのが、分かった。
「ほんとは、こうされたいって思ってたでしょ?」
「旦那さんに、最後にこうやって触れられたの、いつ?」
私はあえて、わずかに意地悪な口調で問いかける。
「……わかんない。もう、ずっと前……かな」
「我慢してたんだよね」
彩香さんは、黙って頷いた。
私は、彼女の肩に手を添え、耳元に顔を近づける。
唇が触れるか触れないかの距離で、ささやく。
「……ねぇ、ほんとは、こうされたいって思ってたでしょ?」
その瞬間、彩香さんの体がびくっと震えた。
声にはならないけれど、心の奥が反応したのが、伝わってくる。
首筋、鎖骨、言葉でほぐす
私は指先で、彼女の首筋をなぞった。
そこから、鎖骨のラインへ。
服の上から、でもゆっくり、確実に。
「私なら……急がないよ。怖がらせたりしない。
ただ、ちゃんと彩香さんを“女”として、見てるってだけ」
手は胸元まで近づいたけど、触れない。
でも、その“触れなさ”が彼女をジワジワと焦らせていく。
「……梓さん……やめたほうが、いいと思う」
その声は、拒絶じゃなかった。
もっと近づきたくて、怖くて、でも求めてる声。
私は彼女の手を取り、そっと指を絡める。
「うん、やめたほうがいいよね。
でも──今日は、もうちょっとだけ、いい?」
彼女は、小さくうなずいた。
体温が交差する一歩手前で
リビングの空気が少し熱を帯び始める。
距離はもう、10cmもない。
吐息が触れ合って、目と目がぶつかって。
キスは、しない。
でもその手前で、止まったまま、お互いの鼓動だけが聞こえる。
「ねえ、彩香さん……」
「……うん……?」
「今度、もっとちゃんと、あなたを気持ちよくしてあげたい」
彩香さんは、そっと目を伏せて──
「……うん……」
微かに震えるその返事が、
女同士の関係が始まる、静かな合図だった。